

食品ロス削減に向けた新たな取り組みを発表するネッスー株式会社
ネッスー株式会社が環境省のモデル事業に参加
ネッスー株式会社は、東京都世田谷区に本社を構え、こどもの機会格差の解消を目指しています。このたび、同社は環境省の「令和7年度 食品の消費行動に伴う食品ロス削減対策導入モデル事業」に選ばれました。この事業では、小売店での販売が難しい生鮮や日配食品を、食品譲渡プラットフォームを通じてこども食堂やひとり親世帯、学生などに提供することを目指しています。
食品ロスの現状と国の方針
環境省が最新の推計値を発表したところによると、2022年度の日本国内における食品ロスは472万トンに達しています。そのうち、236万トンが事業系から発生しているとされています。政府は、この事業系の食品ロスを2030年度までに2000年度比で半減させるという目標を掲げていましたが、当初の目標を約8年前倒しで達成し、新たに60%削減の219万トンを目指します。
家庭や外食産業からの食品ロス削減も求められており、消費者のライフスタイルの変革が重要視されています。そのため、地域の企業や公共団体が連携し、効果的な食品ロス削減策の実践を通じて、地域貢献を目指すモデル事業が公募されました。
ネッスーの取り組み
ネッスーが参加する「部門Ⅱ 売れ残り食品廃棄防止対策導入モデル事業」では、廃棄が決まった生鮮・日配品をこども食堂やひとり親世帯、さらには奨学金を受給する学生などにリアルタイムで提供するプラットフォームを整備しています。昨年度の実証実験の結果を引き続き踏まえた上で、再検証を行いながら、持続可能なサービスへと事業を拡大していく予定です。
食品廃棄の現状と課題
事業系の食品ロスのうち、食品小売業から発生している割合は49万トン(2022年度推計)であり、小売店では需要予測や売れ行きに基づいて様々な対策が取られています。しかし、売れ残りが必ず発生してしまい、廃棄が決まった場合、生鮮や日配食品の場合は消費期限が迫っているため、当日中に団体に提供することが難しいという課題があります。その結果、寄贈されるのは常温保存が可能な加工食品が中心となり、食品ロス削減に繋がらないケースが多発しています。
この問題を解決するため、ネッスーが開発するオンラインプラットフォームを利用することで、リアルタイムでの食品情報の発信が可能になります。これにより、賞味期限が残っているうちにそれを必要とする団体に届けることができ、より多くの食品ロスを削減できると期待されています。
ネッスー株式会社の目指すビジョン
ネッスー株式会社は「こどもの機会格差の解消」をビジョンとして掲げ、活動を進めています。「やさしい社会の実現」のために、地域の企業や団体と協力し、食や体験における格差をなくすさまざまな取り組みを展開している同社。今後も、食品ロス削減事業を通じて、地域に貢献する活動を推進していくようです。
まとめ
ネッスー株式会社の新しい試みは、こどもたちの栄養面を支えるだけでなく、環境にも配慮した持続可能な社会を作るための一助となるでしょう。これからの活動が多くの人々に良い影響を与えることを期待しています。


トピックス(その他)

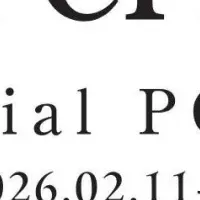



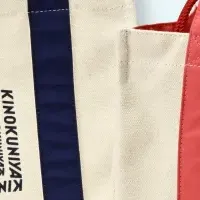
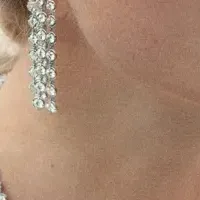


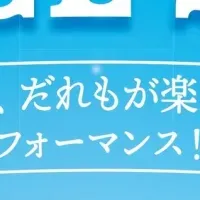
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。