

創業450年を迎える香の老舗『香十』が平安の香りを再現
平安時代の香りを再現した『六種の薫物』
154年の歴史を誇る香の老舗、香十(こうじゅう)が登場します。この度、創業450年を記念し、平安時代に根付いた香り文化を新たに再現した練香『六種の薫物(むくさのたきもの)』が、2025年4月18日より数量限定で発売されます。
歴史ある香十の誕生
香十は1575年に創業し、清和源氏の末裔である安田又右衛門源光弘が初代となります。初期から御所御用を務め、その後も歴代の家康公や宮中に香を納め、名を馳せてきました。特に、江戸時代には香十第八代が茶道界で高名な香の名人として知られ、その後も多くの銘香を献上しています。
厳選された香りの数々
『六種の薫物』は、平安時代の文献から忠実に再現された六種類の練香。その種類は「梅花(ばいか)」「荷葉(かよう)」「侍従(じじゅう)」「菊花(きっか)」「落葉(らくよう)」「黒方(くろぼう)」の六つです。これらはそれぞれ異なる香りの特長を持ち、人々の感性をくすぐります。
各薫物の特徴
- - 梅花(ばいか):源公忠の処方による、梅の花を思わせる華やかな香りが特徴。
- - 荷葉(かよう):山田尼の処方にて、清涼感あふれる蓮の香り。
- - 侍従(じじゅう):八條宮が手がけた落ち着いた秋風を感じさせる香り。
- - 菊花(きっか):白河院、平忠盛の処方による、菊をイメージした優雅な香。
- - 落葉(らくよう):後小松院の落葉の香りが漂う、心を落ち着けてくれる香。
- - 黒方(くろぼう):朱雀院の重厚感あふれる格式高い香り。
伝統を守る製法
『六種の薫物』は、古典文学に記された処方や原料を徹底的に研究・再現し、最上級の香原料を使って丁寧に作られています。調香後は壺に詰めて埋め、一定期間熟成させるという伝統的な製法を経て、特別な練香が完成します。練香は、火を使わずに温めながら楽しむスタイルが特徴で、専用の香炉や茶席で香りを感じることができます。
数量限定の特別な練香
価格は4,950円から5,500円(税込)で、各香りは50個限定の数量販売となっています。この機会にぜひ、歴史ある香十の香りを体験してみてください。
結び
香十の450年という長い歴史の中で培われた技術と感性が結集した『六種の薫物』は、あなたに新たな香りの体験をもたらしてくれることでしょう。この香りの旅をぜひお楽しみください。詳しくは公式サイトでご確認ください: 香十公式サイト 。








トピックス(その他)

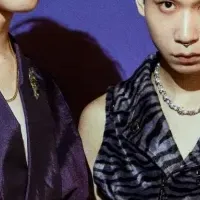


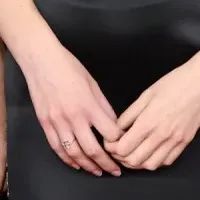


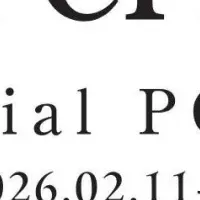


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。